簡単にわかる日本のインテリアの歴史パート3
こんにちは、HaleNoaです(*^-^*)
最近グルメなお話が多いですということを言われました。
なので、本日もグルメなお話をしようと思います(笑)
先日、米子のステーキハウスに行きました。
創業年の老舗ならではの昔ながらのレトロな空間。
レンガを使った歴史を感じるインテリア。これぞ、「ザ・ステーキハウス」!!
私はフィレを食べました。
ジューシーで柔らかく、なので口の中でまとわりつかないから驚き。
ペロッと食べちゃいました。

あ、お店の名前言ってませんでしたね💦
「ステーキハウス精山」です。
思い出すだけで、よだれが出てきます(笑)
是非みなさんも行ってみてくださいね。
私もお仕事頑張って、また自分のご褒美に行きたいと思います。
・・・健康診断の結果があまり良くなかったのでちょっと外食控えて
ロードバイクでも始めようかと悩んでます(笑)
さて、先週に引き続き、日本のインテリアの歴史のつづきを書いていこうと思います。
本日は第三回目なので、この2回でうまくまとめないといけないですね💦
頑張ります。
大正期
1. 家具デザインのパイオニア
この頃、家具デザインにおいて革新的とも言える変化が生じます。
日本の室内空間は、長い時間を経て少しずつその様式を発展させてきたが、明治に入り欧米の様式を受容したことは、それまでの伝統を一新させる出来事でした。
新しい展開が一気に進むのは、大正期になってからです。
斉藤佳三、森谷延雄、梶田恵と行ったデザイナーたちは、生活様式など本質的問題を問いました。
大正デモクラシーの新しく自由な思想や、西洋や前衛芸術の自在な表現と言ったものが流れこみ、ダイナミックな様相を呈していました。
2. 形而工房
独自に家具研究を行っていたグループとして、昭和3年に結成され、昭和12年まで続いた「形而工房」があります。
この集まりは建築家蔵田周忠を中心として、彼が住んでいたアパートメントに集まった人が参加しています。
この集まりは、まず設立した年に「白木屋呉服店」と「紀伊国屋」で試作展を開催します。
特徴は、本格的な機械化に先立って、家具製作の規格化と合理化の方法を模索し、「産業工芸」という分野を見出しました。
当時は、それまでの職人による「一品製作」の工芸から、規格化することで「大量生産」に対応することが時代としても求められていました。
戦後に日本工業規格JISとして改正されることになります。設計図にメートル法表記を採用していました。
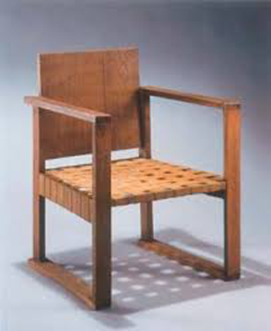
3. 梶田の「工芸家具」
梶田が手がけたのは高度な職人技術を必要でした。
極めて完成度が高く、日本および東洋の家具を研究し、それらの造形やモチーフを自在に組み合わせていました。
西洋の様式の輸入から始まった日本の家具を日本と東洋の伝統と融合し、それを全く違和感ないレベルにまで昇華しました。
通常は梶田が設計し、製作は「寺尾商会」や「コトブキ商会」に外注するなどしていました。
美濃紙にインキングをし、それに水彩で彩色を行ったが、今日まで保存されています。
これは、大正期の社会背景があってのものでありました。

4. 森谷延雄と情緒あふれる家具
童話の中の世界のような詩情溢れる一連のチャーミングな家具です。
大正14年には、国民美術協会展覧会にて、「家具を主とせる食堂書斎及び寝室」を出品し、「眠り姫の寝室」「鳥の書斎」「朱の食堂」と題した三つの発表をしました。
「木の芽舎家具」展には60点ほどが出品され、寝室家具セット、机、書斎、いすから、木工芸品として、子ども用椅子、本棚など住宅用のものを出店しました。
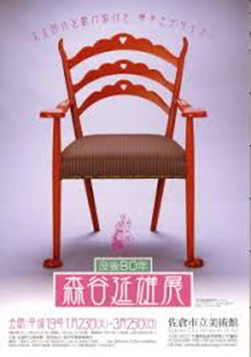
まとめ
大正期は、形而工房が活躍し、後に高度な職人芸の家具が誕生しました。
大正期の盛り上がりに即した出来事でありました。
美術館にも展示されています。
「HaleNoaってどんな家建てるの? vol.73」
線と角のデザインから強調されるモダン建築。
HaleNoa project 設計士
vol.73 デッキテラスの家(外観)



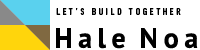




Leave A Comment